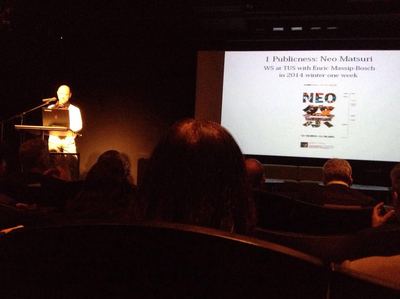« January 2015 | メイン | March 2015 »
February 28, 2015
February 26, 2015
ゲシュタルト的な塊を識別したがるのが人間
ゲシュタルト心理学が示すように、人間はものを識別する(区別する)本能的な能力がある。その場合あるもの(図)をその背景(地)から識別するための条件がいくつかある。図のまとまりがあること。図と字の間に輝度差があることなどである。まとまりがあるという言葉は妙に曖昧な感があるがヒトデのようなものより、饅頭のようなものの方が背景から浮き出やすいということである。この林のように沢山木は一本の木が立っているよりその塊を識別しにくい。
この人間の識別能力はもちろん視覚に限ったものではない。聴覚においても我々は音の塊を聞き分ける。運命のジャジャジャーンを始め、ポップミュージックのサビの部分などをよく覚えているのは聞き分けが容易であると同時にその音の塊は記憶の棚に置いて後日引き出し易いということでもある。味覚で考えてもスープに比べてカレーライスには具というものがありそこに味覚の塊がルーの中に浮遊していることに気づく。では触覚は?無理やりいうなら荒川修作の天命反転住宅は感触の塊がランダムに配置されザラザラ、ツルツル、凸凹、斜めを足の裏で感じ取るように作られている。そこには感触のゲシュタルトがある。焼き鳥屋やうなぎ屋の前には匂いのゲシュタルトが漂っている。
さて一方でこうした5感のゲシュタルトをあえて否定してフラットにしようという行為(表現)も簡単に思い浮かぶ。ミニマリズム音楽、ポタージュスープ、平らで同一素材の床、無臭の空間、モネの絵などである。
五感がゲシュタルトを感じ取る場合その対象の価値が高まる必然はないのだが、往々にして人は識別しやすいものに価値を見出したがる。理由は分かりやすく、人を説得しやすく、記憶に残りやすいからである。モネの絵は当初完成品ではないと酷評されたのも分かりにくいからであろう。ミニマルミュージックを嫌う人のほとんどはメロディーが無いと思うからである。しかしそれが絵画や音楽の価値を下げるこにはなるまい。
こんなことを長々と書いたのは建築の評価もゲシュタルト的に識別しやすいことに重きが置かれる傾向があるということに最近気づいたからである。一昨日の川久保玲のように分かりづらいものの置き方には思考を彷徨わせる意図がある可能性もあるのであり、それこそが受容者の想像性を掻き立てる真の象徴性を兼ね備えた場合もあるのである。
もちろん識別できないことが説明能力のあるいはプレゼン力の不足によるのであれば論外なのだが。
February 25, 2015
やれることをやろう
新刊本の打ち合わせ。本の概略を決めていただいた。定価2400円。初版2000部。サイズは菊判。これは『建築の規則』と同じ大きさなので2冊並んで置ける。全200ページ。ページ750字で下端は少し空けそこに註と参考文献を入れていく。さて自分の写真でもう少し使えるものを探し、章ごとのダイアグラムを作り、最後の対談の相手にお願いをして6月ころにはしたいところである。入稿は10月末。9月は学会、ブエノスアイレスと忙しいので8月が勝負だろうか?進行中の翻訳の脱稿目標が3月。前書きなど入れて、入稿はゴールデンウィーク明けくらいだろうか?篠原先生のアフォリズムの英訳が7月。バルセロナのWSが7月末。そのあたりで二つの建物が竣工。もうひとつの本の入稿が盆前。そして10月末に本書の入稿。時間はあっという間に過ぎていく(Time flies)。先行していろいろなことを終わらせないと終わらない(当たり前だけれど)。
February 24, 2015
ものの置き方
川久保玲が2008年にデトロイトの美術館で展覧会を行っている。タイトルはREFUSING FASHIONである。ファションの拒絶とでも言おうか。そして展覧会場の壁には自分の作品を説明するつもりはないというようなことが書かれている。展覧会を見たわけではないがカタログを見る限り、かなり乱雑に自らのデザインした服が壁に貼り付けられたり、床に置かれたりしている。
ファッションであろうと、絵画であろうと、建築であろうと展示の基本は展示品を分類して、順序を考えてストーリーを見るものに分かってもらおうとするものである。つまり展示品の一つ一つは展示のストーリーを語る言葉でありその言葉同士の接続関係はその並び方である程度推測できるようになっているものである。それはあるときは時系列に並べることにより作者の作品の流れを知らせるものであり、ある時はその作品の特徴ごとに分類することで作者の個性を立体的に鮮明にするものである。
という展示の普通の考え方からするとこれはどうもそういうストーリー(説明)を拒否してランダムに並んでいるように見える。そしてそういう「ストーリーを拒否したものの置き方」というものがあってもいいのだろうと思うに至るわけである。しかし一体そういうものの置き方とは何を欲してなされるのだろうか?(この展覧会がそうなっている確証はまるでないのでこれは想像の域をまったくでないのだが)。
たとえばスーパーマーケットに並ぶ商品というものはだいたい列ごとに商品分類されており、買う人が買いたいものに短時間でたどり着けるようになっている。加えて列と列の関係も近しいもの同士が並んでいる。この列の隣にはきっとこういうものが並んでいるだろうという推測が可能なように配慮されている様に思う。一方ドンキホーテのものの置き方は必ずしもそうではないと言われている。買う人はランダムに並ぶ商品の中をさまよい自ら欲しい物へ辿りつく楽しみ(?)を味わえるようになっている。さらにその彷徨いの中で別の商品に出会う可能性も期待している。
そう考えると川久保がものの置き方の論理性を拒否した(と僕が推測する)こととドンキホーテのランダムな商品を置き方には近しい関係があるように思えてくる。加えてレイアウトというものは必ずしもロジカルに行われているとは限らないししその必要性もない。ということに気づく。ロジックを排除した並び方は思考の彷徨いを誘い、その彷徨いが見る側の内側にある欲求だったり、見方だったりを引っ張り出してくるからである。
最近ものの置き方の持つ意味が気になっている。街並みのようなものを考えてみてもロジックがある場合もあればない場合もあるしどちらがどれだけいいとか悪いとかいうことを言えるわけでもない。
February 23, 2015
ズントーの本
ピーター・ズントー(ツムトア)の文章(『建築を考える』みすず書房2012)を読んでいたら「設計の礎になるのは自分がしてきた建築の経験である」と書いてあって、そういう部分は少なからずあるなと納得する。若い頃はそんなことはないと思っていた。どんなに幼少の頃に貧困な建築環境に育とうと大学教育とそのあとの生活で建築は変わると思ってきたが最近はそりゃそういう人も100人に一人くらいはいるかもしれないが、まあ無理だと思うようになった。槇さんや谷口さんのような建築は彼らのような育ちをしなければできないものである。そう考えるとこの人はこういう幼少期を過ごしてきたのだろうなあと想像出来る建築家はたくさんいるものである。かくいう自分も結局自分の過ごした幼少期のさまざまな体験が建築になっているとしか言いようが無い。それ以上でもそれ以下でもないように思う。もちろんそのつくり方とか表層の部分ではどうであれその真ん中に滲むものはそういうものなのだと思う。
この本のブックデザインシンプルで素敵だと思った。まさにズントーである。彼の幼少期はきっとこういうことだったのだろう。葛西薫のデザインである。
February 22, 2015
翻訳会への道すがら飯田橋に一羽のサギ?
February 21, 2015
篠野先生ありがとうございました
(東工大篠野先生、スチュワート先生、奥山先生、北大小沢先生、筑波大鵜沢先生、竹中藤田さん、鹿島辺見さん、岩下さん、私)
軽井沢の現場から東京駅に戻り、丸善で1時間ほど新刊渉猟してから赤坂四川飯店へ。今晩は東工大の篠野先生の退職をスチュワート研究室一同でお祝いした。我々スチュワート研究室は1984年~1985年の2年間だけ東工大に幻のごとく存在した5人の集団であり、それを指導してくれたのがもちろんスチュワート先生であり、そして篠野助手だった。我々は拙い英語を先生と交わしたあとに篠野先生に対して日本語でひたすら我々の論文の思いの丈をぶつけていたのである。あの時の情熱は半端ではなかった。篠野先生にしては迷惑以外の何ものでもなかったのだろうがそれを真面目に聞いてくれたことで今の僕らがある。こうやって話をすると30年前にワープするのだが、感謝の念は絶えない。こうやってお祝いしてあげられることに喜びを感ずる。ありがとうございました。そして篠野さんの次の人生を応援致します。
スティーブとジョニー
軽井沢現場への数回の往復でリーアンダー・ケイニー著、関美和訳『ジョナサン・アイブー偉大な製品を生み出すアップルの天才デザイナー』日経BP2015を読む。アイブの言葉は自分の博士論文にも引用していた。コンピューターの透明性や、取手のアフォーダンスなど彼のデザインの思想にたいそう驚かされた記憶がある。とてもロジカルなデザイナーであると思っていた。しかしこの本を読むと彼は徹底して機能性と、製作可能性を考えるデザイナーであることが分かる。とは言えクライアントのイエスマンということではない。それゆえに彼は転職の末最後にアップルに来てスティーブのもとで花開くのである。天才と天才の核融合といえば出来過ぎた話のようだがどうもそれが真実みたいである。
February 20, 2015
理科大二部建築学科合同講評会
夜神楽坂キャンパスで理科大二部建築学科の2年生から4年までの後期合同講評会。2年生2課題で4プロジェクト、3年生3課題で6プロジェクト、そして卒計3プロジェクト。審査員は常勤の3人の先生と非常勤の先生たち。新堀さん、河辺さん、浅見さん、蜂屋さん、長谷川さん、木島さん、萩原さん、白子さん、細矢さん、広谷さん、手嶋さん、塩田さん、高橋さんが参加。毎年思うがなかなか豪華な講評会である。
今年選出された作品は形態的に見ると大きく二つに分かれるように思える。一つは敷地に寄り添うもの、もう一つは敷地に寄り添わないものである。一方内容的に見るとそこに建築の重要な要素として人の視線が介在するものとそうでないものがあると思われた。これはつまり僕の中では敷地と人間が建築を分類する大きな分かれ目になっているということの裏返しなのである。そしてでは敷地に寄り添い、人間の視点があることがいい建築なのかというと実はそうでもないということに気がついた
つまり論理的には自分では敷地と人が重要だと分かってはいるがそれを超えたいと思っており、それを刺激するような案が見られたということである。
たまさか審査員の選択で一等賞をとったのが写真の作品である。理科大神楽坂の建物である。2年生にしてこれだけの形が作れるという驚きがある。そしてこの形へ到達するエネルギーと葛藤が垣間見られる。
February 19, 2015
貴重な意見をいただいた
北大集中講義最終日は1時間半設計をした。まあ一つの経験としてみなやってみてもいいのだろうと思った。
北大建築は教員が20人以上いるのだが、意匠の先生は一人で孤軍奮闘している。というわけで学生も意匠の意識はそれほど高くなく、街づくりや歴史の意識の方が高いようである。そういう学生相手にデザインの話をするのにはこちらも試されるのだろうと途中からなんとなくわかって来た。他大でお話するとき、普通は意匠に飢えているような学生を相手にすることが多いわけである。そういう時は何を話しても乾いたスポンジに水を撒くようにスーッと吸い込まれていく。かたや今回のような場合は一見吸い込まれたような水は実は周囲から溢れているのかもしれない。それゆえこういう学生からの授業に対する意見は貴重である。最後に今回の講義を書籍化するためのアドバイスを書いてもらった。活用したい。
7コマ連続講義は初めての経験
北大集中講義二日目9時から6時まで途中昼食一時間を除き8時間連続トーク。こんなぶっ通しで話したのは初めて。さすがに終わるとのどが痛かった。(昨日から合わせると7コマ連続である)内容は建築の条件。全8章を一章一時間。ジェンダー、視覚、主体、消費、倫理、階級、グローバリゼーション、アート。昼食後はお互い眠たかったですが、徐々に挽回し最後の方は駆け足でした。6時に終えて宿題をだして(山城さんの家のプランを暗記する)日建北海道社長の木谷先輩と寿司を食べに。2次会は社長行きつけの素敵なお店「そな田」へ。100年前の民家を改装した内部空間は落ち着く。マスターはなんと元パターナーとのこと。次の札幌があったらまた是非来たい。
February 17, 2015
切実さ
北大集中講義に向かう飛行機の中で今年の芥川賞小野正嗣『九年前の祈り』を読んだ。シングルマザーとなった主人公が外国人との間にできた子供を九州の田舎で育てる話である。その選評を読んでいたら、村上龍と川上弘美が二人共この小説には「切実さ」があると書いていた。そしてその切実さとは「言いたいこと」があるわけでもないし、「伝えたいこと」があることでもない。そうではなくて小説を書くという行為の中にある書く人間の無意識を刺激する装置をどのように使って言葉を紡いだか、その経緯の中に書いた人の「切実さ」が浮かび上がると説明していた。
なるほどこれは建築という行為にも言えるように思った。それは例えば昨日の修士設計などを見ているとそういうことをつくづく感じる。修士設計とはもちろんつくるコンセプトを論文として紡ぎながらそれを建築化していくのだが、文章が建築に1対1対応で変換されるわけではない。そこではスケッチを描きながら、模型を描きながら、「建築する」という行為に内在する設計者の無意識を刺激する装置が駆動しているのである。そしてその装置が紡ぎ出した形や空間の連なりは最終提示された模型やドローイングの中に読み取れるものである。それは必ずしも論理的なものではいのかもしれない。それが「切実さ」なのだろう。そしてそれが伝わるものにしかやはりいい建築は生まれてこないのだろうと私には思える。
修士設計は一生の財産
February 15, 2015
甲府から南大沢へ
9時のあずさで甲府へ。現場定例。外装は張り終わり、内部もボードがだいぶ貼られてきた。昼を食べてからクライアントの車で小さなパン屋を目指して南大沢へ。その名もCicouote bakery(チクテ・ベーカリー)へ。スタッフの佐河君が多摩美の近くに6畳くらいの小さなしかし日本全国に名を馳せるパン屋があったという話をクライアントにしたら、今日行こうということになった。というのも今作っている子供の施設の敷地にパン屋やカフェを作り界隈をつくりたいというのがクライアントの希望だからである。パン屋はしかし現在は引越して少し大きなパン屋となっていた。バゲットが焼きあがるまでコーヒーを飲んで20分待っている間客足は途絶えない。すごいパン屋である。
February 14, 2015
建築における大きさの問題
石上純也『建築の新しい大きさ』青幻舎2010を近美で見つけた。これは2010年に豊田市美術館で行われていた展覧会カタログである。こんな展覧会やっていたとは知らなかった。タイトルにあるようにこれはサイズに対する挑戦である。展示物のタイトルは「雲を積層する」「森を計画する」「地平線をつくる」「空に住む」「雨を建てる」得体の知れない大きさ、無数の縦の線、無限の横の線、針のような細さ、それらは自然界にはあっても人工物としては成立しなかったようななにかなのである。
僕は見ていないので分からないのだが、説明を書いている青木淳が言うようにこれは模型ではあるがそれは建築の代替物としての模型ではなくそれ自体が建築なのである。
昔博士論文を書いた時にそれまで東大でやっていた「建築の質量と形式」という講義録を整理した。その時にそこに足りないのは建築の大きさだということに気づき一章設けた。というわけでこの石上さんの挑戦はとてもよく理解できるし、そこに展示されていただろうものにとても興味がある。見られなかったけれど少なくともこのカタログに出会えて良かった。
February 13, 2015
西荻にはいい店が多い
February 12, 2015
ファビエールのお別れ会
午後の大学の会議、雑用を終えてからアルゼンチン大使館へ。ハビエル・ゴリシェフスキ文化参事官の退任お祝いのディナーパーティーである。ハビエルには去年ロベルトやダニエルがアルゼンチンから来た時に夕食に招待していただいた。加えて彼と彼の部下の柏倉さんがワークショップのオリエンテーション、最後のクリティーク、そしてセルバンテス文化センターでのシンポジウムそしてその夕食まで濃密にお付き合いいただき、クリティークではアルゼンチンの経済状況を踏まえた専門的な批評まで頂いた。国際ワークショップをするとこういうプラスアルファの人間関係が生まれ自分の世界が広がるものである。さて大使館についてみると、私は7時ぴったりに着いたのに誰もいない。あれっ時間を間違えたのかと思ったら皆のんびりやってくるのですよと柏倉さんが言う。7時半くらいに皆さん来たところで大使がファビエールに感謝の言葉を述べなんとなく食事が始まる。今回はファビエールの懇意にしている人だけ呼んだということで20名くらいしかいない。そのおかげで皆さんとゆっくり話ができた。政治的な関係者はほとんどいなくて、文化的な方ばかりである。原美術館の副館長、世田谷パブリックシアターのダンスキュレーター、写真美術館の映像プログラマー、写真家、音響プロデューサー、富士吉田でなにかやりませんかと言うと、皆さん興味津々であった。時を忘れて語ることができた。こういうパーティーの中では珍しく大変楽しいものでした。ファビエールとは9月にまたお会いできるとうれいしい。ご招待いただき感謝。
セルバンテス文化センターでのシンポジウムの後で一杯
February 10, 2015
チャラヤンの作品集長方形じゃない
ソーシャル化する音楽
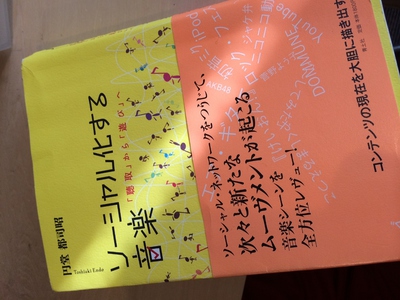
建築がソーシャル化する昨今、音楽もそうなのかと思い『ソーシャル化する音楽』円堂郡司昭著、青土社2013を読んでみた。これは著者自ら言うように渡辺裕『聴衆の誕生』を受けて音楽が音楽を一生懸命聞き取る「聴取」することから変化し始めたその先についてポピュラーミュージックについて分析している本である。そのポイントは音楽が「分割」「変身」「合体」を遂げているというものである。分割とはアルバムという概念が壊れ聴く人が聴きたいものだけをネット上から獲得するようになったこと。変身とは椹木野衣が『シミュレーショニズム』で言うようにリミックス、カットアップ、カバーと言った手法に加え着メロなどに変化を遂げていること。そして合体とは演奏する人聴く人という境界が無くなりカラオケなどで聴く人が演奏する人と一体となる現象が様々見られるということである。こうした変化のひとつの原因はネットの普及であり、音楽が社会を網目状につなぐネットワークの中で変化していると言うわけである。所謂建築のソーシャル化はもう少し政治経済と絡んだ話なので同じソーシャルでもちょっと違うということである。
February 9, 2015
修論チェック
今日は修士論文の仮綴じ提出日。提出後僕が主査している自分の研究室の論文と副査をしているほかの研究室の論文が届けられる。全部で15個くらい。今日は2時からの会議を終えてさっさと帰りやることがあったのだが、これらに目を通すのを今日やらないとやる日がない。ということで一気に全部読んでコメント書いて著者に渡した。修士ともなるとそれなりによくかけているものが多いが、これは卒論とどう違うのと思うものも少々ある。まあ今日はまだ仮綴じということで最終に期待しよう。帰路、金町で電車に乗ったら坂牛研OBの鬼沢くんにばったり会った。現場の帰りとのこと。入社2年目でプロジェクトを3つも持って奔走しているとのこと。なかなか勉強になるな。彼の事務所のシステムが面白い。構造5人、意匠5人いて構造は他事務所の仕事も受けているとのこと。一体どんな建物作っているのだろうか?彼は奥さんも坂牛研。研究研カップルが結婚した第一号だろうか?もう子供もいるというから大変だ。幸せに。
February 8, 2015
このペンダント秀逸
久しく縁の無かったアルフレックスにクライアントとやってきた。すでに一年間相談してきた家具の最終決定ということでダイニングテーブル、ダイニングチェア、スツール、ソファ、クッション、カーペット、ソファ用のテーブル、ダイニングペンダントなどなど、、、、、を見にやってきた。既にクライアントと家具屋さんで決定されていたものの材質、色を最終決定するために設計が模型を持ち込み、確認をした。さすがに量も多くて2時から始めても5時半までかかった。いいものを選ぶことができた。ペンダントは違うところで選んだそうだが、たまさかアルフレックスにぶら下がっていた。直径12センチガラス厚が3センチくらいあり質感がある。12ボルトハロゲンを差し込むソケット部が鋳物で実にいいデザインである。これはいい。
February 7, 2015
やっぱりダメだな
先日みかんぐみの竹内さんに進められた宇沢弘文、内橋克人『始まっている未来-新しい経済学は可能か』岩波書店2009を風呂で読みながら驚いた。それはローマ法王が100年に一回出す「レールム・ノヴァルム」というお言葉の20世紀版を作ったのが宇沢氏だったという事実が書かれていたからである。僕はこの言葉を数年前に知ってとても感動した。レールム・ノヴァルムの19世紀版は1891年レオ13世が出されそれは「資本主義の弊害と社会主義の幻想」というもので20世紀版はそれから100年たちヨハネ・パウロ2世が出し「社会主義の弊害と資本主義の幻想」というものだったのである。なんとタイムリーなことを言うものだと感心していたのだが、それを考えたのがキリスト教徒でもない宇沢氏だったと本人自ら本書に書いていた。改めて宇沢氏の世界的な評価の高さを感じるものである。
そしてこれを読みながら宇沢氏がシカゴ大学で同僚としてのミルトン・フリードマンを学者の風上にも置けず尚且つ人間的にも品格を欠きその教え子であるシカゴボーイズの先頭にいるのが竹中平蔵でありその取り巻きたちが政府に媚びて経済学を社会のための何の力にもできなかった経過がよくわかった(オヤジが会うたびに徹底して批判していた竹中平蔵のダメさがよくわかる)。
ところで僕は現在のネオ・リベラリズムに反対する書も賛成する書も読んでみたし、賛成する人間とも話をする(私の研究室にはニューヨーク大学の経済学部出身でハイエク、フリードマンをよく知る学生がいたりする)のだが、その結果私の今の気持ちはこうなってきた。ネオリベラリズムの中心的コンセプトである競争原理であるが、これはマクロに見たら反対、ミクロに見たら賛成である。競争原理を原理的にすべてに応用する、しないと決めることが原理的なのである。
私は昔からリバタリアンである。しかしこれはとても私的な感情として生かしておけばいいと思っている。例えばすでに戦う同じ土俵に乗っかれた人間同士は戦えばいい。その範囲では競争原理でいい。しかし視点をもう少しマクロにとったときは様々な別な条件があるのでありそれを知らずに一律に競争原理を持ち込むことは想像力の欠如としか言いようがないだろう。私の知るリバタリアンはどうしてああも原理的なのだろうか?競争原理と心中したいような人間に限って所属社会における評価が低い。きっとそれにたいするルサンチマンがそう言わせているのであろう。競争原理を徹底してくれれば俺はもっと評価されるはずだというよな、、、我が国の首相も世界での評価が低いことへのルサンチマンがそう言わせているような気さえする。弱い犬ほどよく吠える。
房総半島には春が?
February 6, 2015
TYIN
アルゼンチンビエンナーレのカタログが送られてきた
アルゼンチンから分厚い小包が届いた。開けてみるとアルゼンチン建築ビエンナーレの展覧会カタログである。昨年その展覧会に出品するためのパネルデーターA1サイズ6枚分を送っていた。このビエンナーレはなかなか豪華で四つのテーマに4人のゲストを招待した。伝統と創造というテーマにスペインからフランシスコ・マンガード、技術:職人技と工業技術にブラジルからパウロ・メンデス・ダ・ロシャ、サステナビリティ:自然と社会にフランスからアン・ロカトン、都市の風景に日本から妹島さんである。各テーマごとに会場が異なり、そこに招待作家の作品が国外から8国内から8程度A1サイズそれぞれ6枚展示されたようである。それがカタログとなって送られてきた。全300ページくらいある分厚いもの。私の場合先方のキュレーターが「赤い家」を指定してきていた。そしてそれは伝統と創造のテーマにくくられていた。それがどういう理由なのかはよくわからない。
カタログも美しいレイアウトだが、HPもとても見やすく美しい。是非下記をクリック下さい。
http://biaar.com/realizaciones/red-house/
February 5, 2015
無理なら最初に言って
いつでも期待していたのにそうならなくてがっかりすることはある。人生は悲喜交々である。コンペに入る入らない、いい仕事が入ったり逃げていったり、などなどまあ数えたらキリがないのだが、最近二つかなり引っ張られた挙句に「できません」と言われ愕然としたことがある。一つはとある理由で人を探し、これはと思う人を1年追っかけて食事も何度かしたり、メールでもいろいろやり取りした挙句に「できません」と断られたこと。もう一つは拙著『建築の規則』の要約英訳をとある方に春にお願いし、夏に出来ると言われ、秋に伸び、冬まで待ち、そして最後に「できません」と返事をもらったことである。うーんできないなら最初に言えよと言いたくなるのだが、言えない事情もあるのだろうか?前者は状況を鑑みるにある程度仕方ないかもしれないけれど、後者はれっきとしたビジネスである。納入期限を無視した挙句に納入しないのだからそれは罪だ。
それにしてもプロポーズの答えを一年引っ張って最後に無理ですというのに等しいね。そんな経験ちょっと辛い。
人生いつまでか?
February 3, 2015
ココナッツオイルでアルツハイマー予防
February 2, 2015
富士吉田の空き工場コンヴァージョンコンペ最優秀
去年から富士吉田市のデザインコンペを研究室でやっていた。とは言っても実質的には助手の佐河君、院生でオーストリア帰りの中川君、大村君の3人が泊まり込みで制作。130近くの出品がありファイナル3チームに残り今日がイトーキで公開ヒアリング。僕は大学院留学生試験があり行けなかったのだが、夕方彼らから吉報が届く。このコンペは富士吉田にある製氷工場(と言っても鉄骨3階建ての小さな建物)をコンヴァージョンして地域の核となるような場を作るもの。我々の案は閉鎖的な工場建築を街に開くために木のルーバートンネルで1階から3階までを繋げようというもの。1500万の予算でどこまでできるかはやや不安だが、この夏オープンを目指して実施設計を進めることとなった。富士吉田にはまだまだ空家があり、継続的にこうした遺産を有効利用する計画もあるようである。
February 1, 2015
人生65から
こっちでもそっちでもない表象
ルイジ・ギッリという写真家がいる。その昔どこかで見た気がしていてその透明な空気感が好きだったのだが、みすず書房から『ルイジ・ギッリ 写真講義』(ジュリオ・ビッザーリ/パオロ・バルバロ監修菅野有美訳みすず書房2014)なる本が出版された。これは地元の専門学校で行った写真の講義である。素敵な(というか何気ない)装丁で昔の記憶も重なり気に入って購入し少しずつ読んでいた。その中で彼は自分の写真は自分の世界でもなければ客観的な実在でもないと言っている。そうなんだ。この透明感は撮る人のエゴでもなければで場所の持つしつこさでもない。あるいはその逆かもしれない。そのどちらでもない、どちらにもこけそうな危うさがギッリの魅力である。と思っていたら青木淳さんが読売新聞の書評に同様なことを書かれていた。