球体二元論
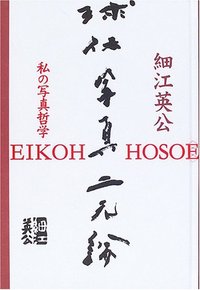
細江英公の『球体写真二元論』を読んだ。写真において二元論とは何かという細江の問いなのである。彼の写真集に『薔薇刑』(1963)という三島由紀夫を撮ったものがある。その中に「細江英公序説」とい三島の文章がある。そこで三島は「写真とは記録性と證言性(証言性)の二者択一」だと書いている。これは古典的な写真論と同じことを言っているそうで一般には「記録性」と「表現性」と言うそうだ。また1978年にはMOMAの写真部長ジョン・シャカフスキーが「写真を自己表現(self expression)と調査(exploration)の二種類に大別」したそうである。しかし細江は写真とはこのどちらかではなくその両方であり、その両極を持つ地球の上をどちらかの極に引き寄せられながら作り上げるもので、どちらによるかは被写体によるというのである。
この両極説は僕のモノサシとまったく同じ考えでありとてもびっくりしたのである。更に言うと細江のこの考えはアメリカの歴史心理学者ロバート・リフトンが『Protean self』のなかで記していると言う。そこではこの激変する世界に生き残るためには変幻自在に生きる術が必要でその術をギリシャ神話のプロテウス神になぞらえて「proteanーself」(プロテウス的自己)と呼んでいるそうである。とても興味深い。

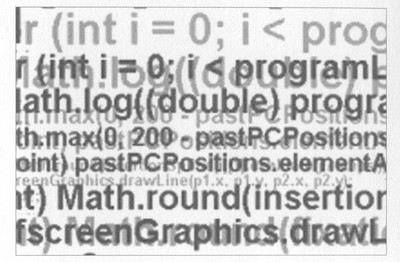
![go_298_04[1].jpg](http://ofda.jp/column/go_298_04%5B1%5D.jpg)
![go_298_07[1].jpg](http://ofda.jp/column/go_298_07%5B1%5D-thumb.jpg)