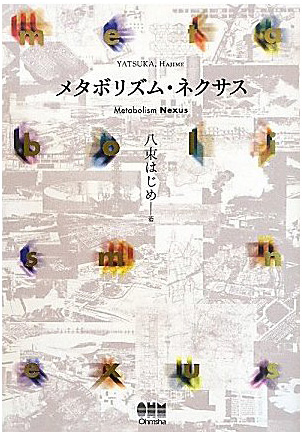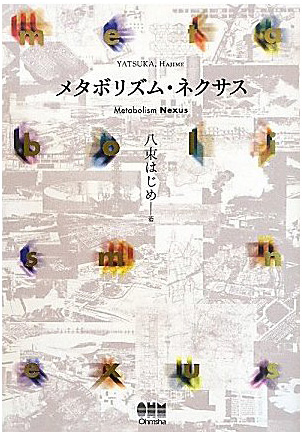
八束はじめ『メタボリズム・ネクサス』(オーム社、2011.4.23刊) |
1. ネクサス(つながり)の意味するところ
本書は著者八束はじめ氏の前著『メタボリズム──一九六〇年代
日本の建築アヴァンギャルド』INAX叢書1997(吉松秀樹と共著)に続くメタボリズム研究書である。前著がメタボリスト個々の活動に焦点を当てていたのに対し、本書はタイトルの「ネクサス」(つながり)が示す通りメタボリズムの関連系に重点が置かれている。よってメタボリズムのみが描かれているわけではない。関連系の主軸は中心的メタボリストの師、丹下健三である。その意味ではメタボリズムという局面で切り取った丹下論とも言えるだろう。しかしネクサス(つながり)の持つ意味はそれにとどまらず、さまざまな事件の因果の可能性を星座の如く布置した著者の描き方をも示すものである。
よく言われることだが、ある芸術運動の輪郭(何処までがその領域内で何処からがその外であるか)を見定めるのは難しい。如何なる場合も中心がありその周縁がある。加えてメタボリズムは初期メンバーである菊竹清訓、黒川紀章、大高正人、槇文彦といった面々がそれぞれの理論を展開した総合であり、ひとつの強い理念に基づく活動ではない。メタボリズムの代名詞のようなカプセル、そしてメタボリズム(新陳代謝)の意味自体もメタボリズムという事象の一側面でしかない。よってその活動の総体を既述の通り星座を布置するが如く(ネクサスとして)描いたその描き方は著者の卓見である。
2. メタボリズムのアクチュアリティ
上のように書くと本書はメタボリズムにまつわる膨大なデーターベースであるかのような誤解を招きそうなので、著者が読者に期待する本書の目的についても記しておきたい。
著者は国家を擬人化し、フロイトの用語法を援用して国家の規範を「スーパーエゴ:超自我」、その対極にある欲望の原理を「イド」、そのイドを理性的にコントロールするものを「エゴ:自我」と呼ぶ。そして近代日本における建築家はメタボリズム(60年代)の時代まで建築的スーパーエゴ(規範)を掲げ、それを形(アルターエゴ)にしてきたと述べる。その時代までの建築家に建築的スーパーエゴが見えていたのはもちろん彼らの内面にアプリオリにそれらが胚胎していたからではない。文化としてのスーパーエゴが建築的スーパーエゴを喚起した結果である。その中核をなす文化的事件が「近代の超克」であり「世界史の哲学」である。これらはいずれも戦争へ突入する時期に世界の中での日本のプレゼンスを再確認し日本の参戦を正当化する言説でもあった★1。1940年代におけるこれらの文化的スーパーエゴをアルターエゴ化した建築家のひとりは丹下健三であり、20年後にその弟子たちは丹下のこうしたDNAを受け継ぐことになる。
著者はメタボリズム以降70年代は建築的スーパーエゴが後景化し、磯崎新、篠原一男という2人の建築家が「エゴ」を語る時代となったと述べ、そして世紀をまたぎ、現在では「エゴ」を通り過ぎ欲望「イド」のレベルで作られる建築が横行する時代になったことを嘆く。「近年の、とりわけ日本に見られる、繊細で柔軟だが、超自我とは無縁で個人的な身体感覚のみによって成立しているような「建築作品」は......やはり無意識(イド)の産物であることによってネオリベラリズムの無神経な都市を補完している......補完は批判ではない」と現状を厳しく批判する★2。
またネット上のサイト《Art and Architecture Review》に「こんな時だからこそ、カプセルばかりでなくメガストラクチャーを」と題した論考を寄稿し、19世紀前半の理想の乏しいドイツ文化の総称である「ビーダー・マイヤー」を現代建築の閉塞感と重ね合わせ、これを超えねばならないと読者を鼓舞する★3。特に震災後の日本において真に考えなければならないことはソフトの意味でのメガストラクチャではないかと主張する。つまり本書を通して八束氏が読者に期待することはメタボリスト達が持っていた「スーパーエゴへの意志」に学べということなのである。
|